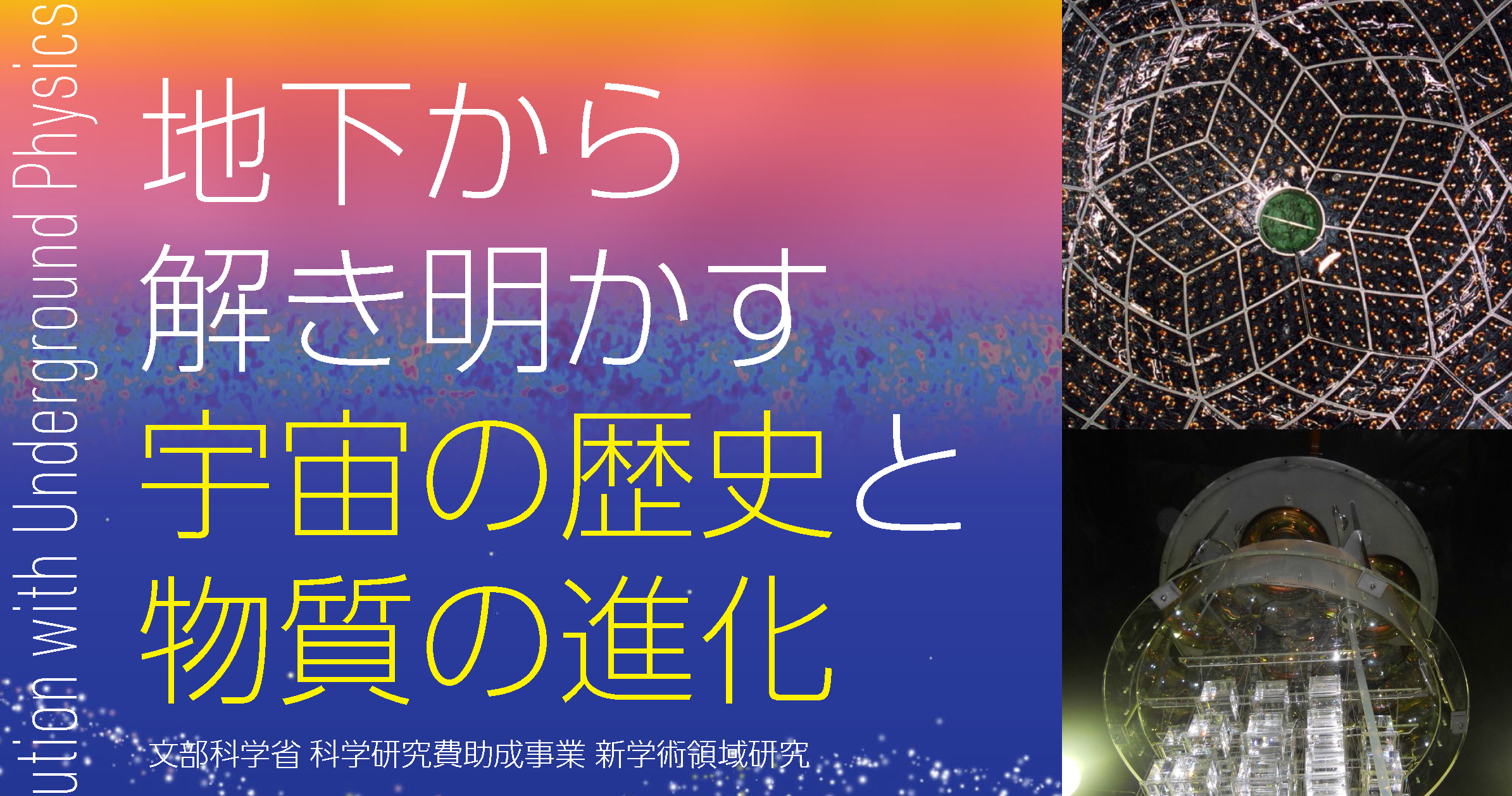計画研究 D02 極低温技術による宇宙素粒子研究の高感度化
本計画研究は、本領域で発展させる低バックグラウンド技術を利用し、計画研究 D01 と協力して、さらに新しく極低温技術を取り込んだ次世代超高感度大型検出装置実現に向けた極低放射能・極低温・超強磁場環境を神岡地下実験室において整備し、共通の技術的課題の解決と計測技術開発を推進する。結果として、ニュートリノマヨラナ性検証(項目 A)および暗黒物質探索(項目 B)の高感度化に寄与するとともに、将来の次世代大型検出器計画の基礎研究と技術的提案を目指す。
(二重ベータ崩壊探索への応用)項目 A で取り組む0ν2β探索実験の高感度化を目指すうえでバックグラウンドの低減は決定的に重要である。計画研究 D01 の技術による放射性不純物によるバックグラウンドの低減は有効であるが、宇宙線核破砕反応によるバックグラウンドや標準理論枠内で起こる二重ベータ崩壊の0ν2β領域への染み込み事象は低減できない。この課題を解決するため、多様な温度センサー・崩壊核種を含む結晶検出器と極低温技術を組み合わせた蛍光熱量検出器の開発を行い、検出器の高エネルギー分解能化を実現する。飛躍的なバックグラウンド低減手法の提供により、順階層領域での探索も見据えた次世代0ν2β測定装置の提案・検証実験を行う。
(暗黒物質探索への応用)項目 B で取り組む暗黒物質探索の高度化を進めるために、極低温技術を利用した新しい粒子識別手法と、超伝導センサーによる微弱な信号検出技術を開発し、極低放射能環境下において、低質量 WIMPs などの未探索領域の探索が可能であることを実証する。また、素粒子物理学的見地から重要視されているアクシオンの探索技術開発を行うため、探索に不可欠な強磁場下でのマイクロ波技術の開発研究を遂行する。特に 5~8.5GHz 領域において、強磁場環境下で Q=106 の共振空胴を実現し、アクシオン探索の高感度化への道筋を切り拓く。計画研究 B01、B02 と相補的な実験的探索の枠組みを構築し、理論班との連携を通して暗黒物質の総合的理解の促進につなげる。
メンバー
[代表]

吉田斉 Sei, YOSHIDA
大阪大学 准教授 原子核実験
総括、0ν2β実験
[分担]
(二重ベータ崩壊探索への応用)項目 A で取り組む0ν2β探索実験の高感度化を目指すうえでバックグラウンドの低減は決定的に重要である。計画研究 D01 の技術による放射性不純物によるバックグラウンドの低減は有効であるが、宇宙線核破砕反応によるバックグラウンドや標準理論枠内で起こる二重ベータ崩壊の0ν2β領域への染み込み事象は低減できない。この課題を解決するため、多様な温度センサー・崩壊核種を含む結晶検出器と極低温技術を組み合わせた蛍光熱量検出器の開発を行い、検出器の高エネルギー分解能化を実現する。飛躍的なバックグラウンド低減手法の提供により、順階層領域での探索も見据えた次世代0ν2β測定装置の提案・検証実験を行う。
(暗黒物質探索への応用)項目 B で取り組む暗黒物質探索の高度化を進めるために、極低温技術を利用した新しい粒子識別手法と、超伝導センサーによる微弱な信号検出技術を開発し、極低放射能環境下において、低質量 WIMPs などの未探索領域の探索が可能であることを実証する。また、素粒子物理学的見地から重要視されているアクシオンの探索技術開発を行うため、探索に不可欠な強磁場下でのマイクロ波技術の開発研究を遂行する。特に 5~8.5GHz 領域において、強磁場環境下で Q=106 の共振空胴を実現し、アクシオン探索の高感度化への道筋を切り拓く。計画研究 B01、B02 と相補的な実験的探索の枠組みを構築し、理論班との連携を通して暗黒物質の総合的理解の促進につなげる。
[代表]

吉田斉 Sei, YOSHIDA
大阪大学 准教授 原子核実験
総括、0ν2β実験
[分担]
石徹白晃治 Koji, ISHIDOSHIRO
東北大学 助教 素粒子実験
暗黒物質探索
岸本康宏 Yasuhiro, KISHIMOTO
東北大学 教授 宇宙線実験
アクシオン探索
美馬覚 Satoru, MIMA
理化学研究所 研究員 素粒子実験
超伝導センサー、計測技術開発
東北大学 助教 素粒子実験
暗黒物質探索
岸本康宏 Yasuhiro, KISHIMOTO
東北大学 教授 宇宙線実験
アクシオン探索
美馬覚 Satoru, MIMA
理化学研究所 研究員 素粒子実験
超伝導センサー、計測技術開発