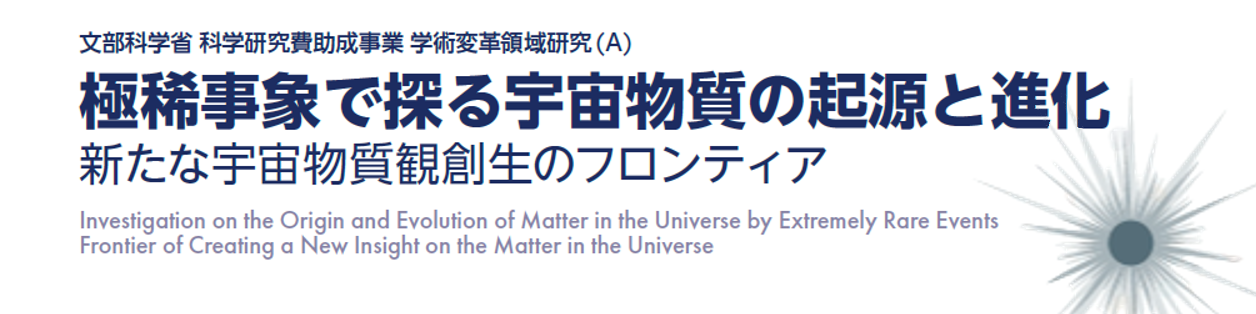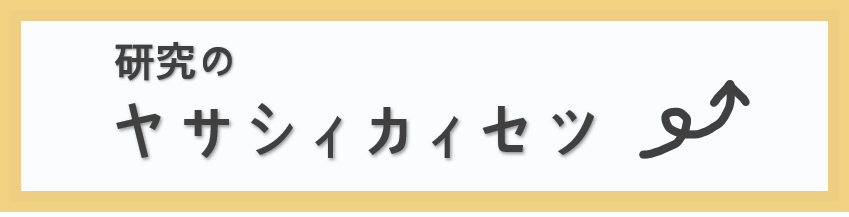オンラインセミナー
Hitachi Seminar 2025
暗黒物質探索で検出器応答を考える上で重要になる放射性物性について、月出さんに解説していただきます。 zoomで約1か月に1度くらいの頻度で実施予定です。2月16-17日には東北大にて月出さんをお呼びして対面の研究会を予定しています(ウェブページ)。
告知は高エネルギー物理学研究者会議、宇宙線研究者会議、学術変革領域「極稀事象で探る宇宙物質の起源と進化」のメーリングリストにて行っています。
暗黒物質探索で検出器応答を考える上で重要になる放射性物性について、月出さんに解説していただきます。 zoomで約1か月に1度くらいの頻度で実施予定です。2月16-17日には東北大にて月出さんをお呼びして対面の研究会を予定しています(ウェブページ)。
告知は高エネルギー物理学研究者会議、宇宙線研究者会議、学術変革領域「極稀事象で探る宇宙物質の起源と進化」のメーリングリストにて行っています。
| 第1回 | 2025.08.01 13:00-14:30 zoom | 録画 (mp4) 講演資料 (PDF) |
|---|---|---|
| 第2回 | 2025.09.04 14:00-15:30 zoom | 録画 (mp4) 講演資料 (PDF) |
| 第3回 | 2025.10.10 14:00-15:30 zoom | 録画 (mp4) 講演資料 (PDF) 補足資料 (PDF) |
| 第4回 | 2025.12.05 15:30-17:00 zoom | 録画 (mp4) 講演資料 (PDF) |
| 第5回 | 2026.01.16 15:30-17:00 zoom | 録画 (mp4) 講演資料 (PDF) |
目次
| 1. | 序論 |
| 1.1 | 阻止能と断面積 |
| 1.2 | 重粒子の阻止能 古典論 |
| 1.3 | 光吸収断面積と振動子強度 |
| 2. | 原子模型 |
| 2.1 | 電子ガス |
| 2.2 | Thomas-Fermi模型 |
| 3. | 重粒子の阻止能 |
| 3.1 | 荷電粒子と原子の衝突 摂動論 |
| 3.2 | 高速重粒子の阻止能 Betheの式 |
| 3.3 | 高速重粒子の阻止能 Betheの式の拡張 |
| 3.4 | 重粒子の飛跡構造 I |
| 4. | 低速重粒子の阻止能 |
| 4.1 | Rutherford 散乱 |
| 4.2 | 核的阻止能 |
| 4.3 | 電子的阻止能 電子移動 (Firsov理論) |
| 4.4 | 電子的阻止能 誘電応答 (Lindhard理論) |
| 4.5 | MO理論 |
| 5. | 低速重粒子によるエネルギー付与 |
| 5.1 | エネルギー分配 核的消光因子 |
| 5.2 | 電子的LETとBragg-like曲線 |
| 5.3 | Angular Scattering |
| 5.4 | アルファ崩壊の際の反跳重粒子 |
セミナー紹介
暗黒物質直接探索では低エネルギー原子核の媒質中での振る舞いを理解することが非常に重要です。 暗黒物質に散乱された原子核はエネルギーが低く、フェルミ速度以下の原子核にはベーテブロッホの式は適用できないですし、エネルギー損失がどういう形態に行くのか(電離・発光・熱・etc)はエネルギー閾値等にもかかわるため検出器設計にとても重要です。 実験屋は中性子を照射するなどしてそれらの値を測定しますが、閾値ぎりぎりでの振る舞いを予測したり、外挿しているパラメータの正当性を持たせたり、新しい媒質を考えたりするときには何かしらのボトムアップなモデルが欲しいところです。 例えば、この分野ではSRIMというエネルギー損失計算ツールを使うことがありますが、インプットパラメータや適用条件が合っているかをきちんと判断して使うのはそんなに簡単ではないと思っています。SRIMがどういうモデルで計算をしているのかを理解するためにも、放射線物性の基礎を学ぶ意義があると思います。放射性物性の教科書として、月出さんには「放射線物性1(伊藤憲昭著)」「原子衝突(高柳和夫著)」を挙げていただいており、目次を見るだけでも暗黒物質探索の検出器応答と関連しそうな項目が多いことが分かります。(ちなみに、「放射線物性2」も読みたいのですが、発行されてないっぽいです。どなたか情報持ってる人がいれば教えてください。)
月出さんは、放射性物性分野でありながら、暗黒物質探索業界に来て、低エネルギー原子核の媒質中での振る舞いについて議論されてきました。 当時自分が学生だった頃は、(大変失礼ながら)なにか難しい話をしてるな、くらいの認識でしたが、今になってみると非常に重要かつここを極めれば検出器的なブレークスルーも得られそうな雰囲気さえ感じています。 幸運にも月出さんとは早稲田のXeSATで色々しゃべったのをきっかけに定期的に連絡をとっており、自分の中でも体系的に学びたいと感じたことから今回の概説を依頼するに至りました。
今回、放射線物性の基礎を暗黒物質分野内で共有することにより、研究会等でより高度な議論を展開したり、検出器性能の理解や性能向上がなされたらいいなと思っています。
月出さんは、放射性物性分野でありながら、暗黒物質探索業界に来て、低エネルギー原子核の媒質中での振る舞いについて議論されてきました。 当時自分が学生だった頃は、(大変失礼ながら)なにか難しい話をしてるな、くらいの認識でしたが、今になってみると非常に重要かつここを極めれば検出器的なブレークスルーも得られそうな雰囲気さえ感じています。 幸運にも月出さんとは早稲田のXeSATで色々しゃべったのをきっかけに定期的に連絡をとっており、自分の中でも体系的に学びたいと感じたことから今回の概説を依頼するに至りました。
今回、放射線物性の基礎を暗黒物質分野内で共有することにより、研究会等でより高度な議論を展開したり、検出器性能の理解や性能向上がなされたらいいなと思っています。
関連情報
書籍
| タイトル | 著者 | 内容紹介 |
|---|---|---|
| 放射線物性1 | 伊藤憲昭 |  今回のセミナーに沿った内容が記載されている。2巻はまだ出てないっぽい。 今回のセミナーに沿った内容が記載されている。2巻はまだ出てないっぽい。 |
| 原子衝突 | 高柳和夫 |  放射線物性分野の古くからある教科書。 放射線物性分野の古くからある教科書。 |
| SRIM book | J.F.Zeigler | 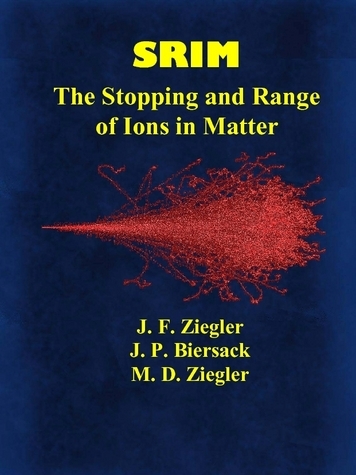 エネルギー損失の計算ツールSRIMについての解説本。 エネルギー損失の計算ツールSRIMについての解説本。 |
ウェブ
| タイトル | 内容紹介 |
|---|---|
| イオンビーム工学入門 (PDF) | 放射線物性についてのまとめ資料。 |
| 暗黒物質探索実験と低速重粒子の検出器物性(月出章 著) (PDF) | 月出さんの記事。 |
| 希ガス液体の放射線効果(月出章 著) | 月出さんの記事。 |
世話人
中村輝石(東北大)kiseki epx.phys.tohoku.ac.jp
epx.phys.tohoku.ac.jp
山下雅樹(名古屋大)
 epx.phys.tohoku.ac.jp
epx.phys.tohoku.ac.jp山下雅樹(名古屋大)
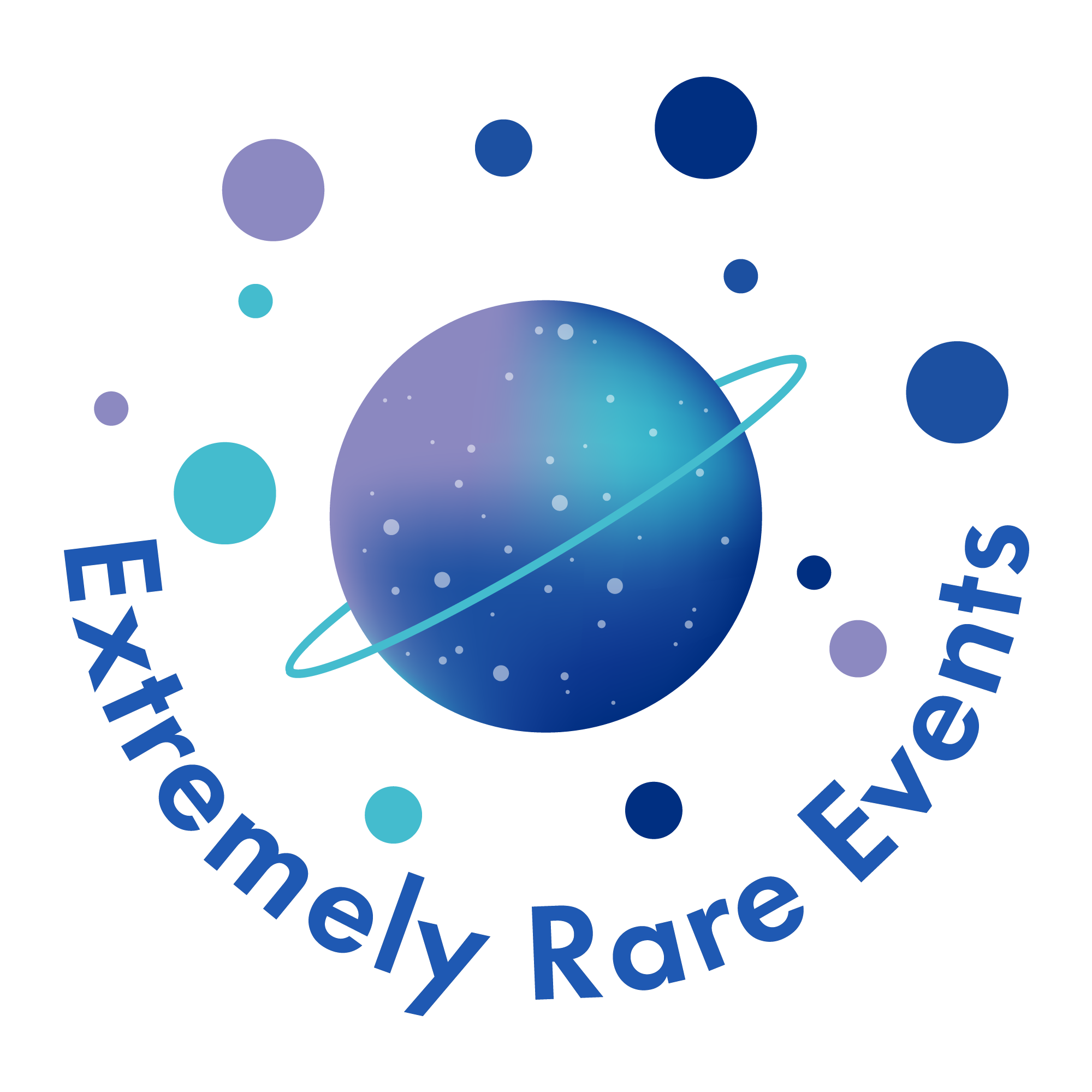
 文部科学省 科学研究費助成事業 学術変革領域研究(A)
文部科学省 科学研究費助成事業 学術変革領域研究(A)